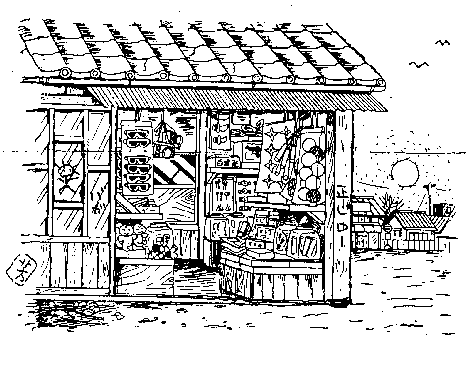花咲和三郎、二十八歳。小学校の五年梅組を担任している。
彼の性格は熱血で、ちょっと抜けたところもあり、子供たちには根強い人気があった。
若くて明るい和三郎先生のクラスは五十五人。
昭和三十年代半ば、授業中の教室の窓からは、刈り上げられた田圃(たんぼ)が見え、
干された稲の束の向こうには、市電の緑が見えかくれしながら走っていた。
梅組五十五人の「梅っ子」は、合唱コンクールでも、雪像コンクールでもクラス一丸となって一位を取り、
百十の瞳がきらきら輝き、教室がはじけそうに膨らんでいた。
そのひとつ置いたクラスは、藤組だった。
和三郎先生の梅組のざわめきは、一つおいた藤組にまでも届き「藤っ子」全員に、
万感こもった小さなためいきを「ふっ」と、つかせてしまうのであった。
ほかと違うことが最大の失態だと思っている、女先生が担任する、藤組。
この藤組は合唱コンクールで、
「こだまがひびく、山から山へとひ・び・くぅ」
という歌を、輪唱も二部合唱も無く歌い、
七秒くらいで終わってしまい、全校で最下位になったという過去を持つ。
雪像コンクールでは梅組の立派な洋風のお城に対し、
「雪うさぎ」を、十日の製作期間なのに
土曜日の午後二時間ぐらいで完成させてしまって時間を持て余し、
せめて、お盆だけでも追加させてくれ、という子供達の嘆願に先生は
「そんなこと、するもんじゃありません。キーッ!」
と、一言で却下してしまったというエピソードも持つ。
ふだんは
「静かに座っていなさい。キーッ」
と言う以外に強い意思を示さぬ女先生だったが、それ以外に示した強い意思といえば、
合唱コンクールで「こだま」を歌うこと、
雪像は「雪うさぎ」を作ること(しかもお盆抜き)だった。
どちらも、クラスで話し合って決めることになっていたのに・・・。
そして全校最下位。
ほかと違いすぎるほど違うこのクラス。
それもただの外し方ではなかった。
人と違わぬように生きようとするこの先生、
そうしようとすればするほど違ってくる結末におどおどした。
しかし、藤組の五十六人はそれはそれは元気だった。
放課後行う学級対抗の野球や、個人の成績が累計される運動会ではいつも一位で、
女先生はますますドギマギしたが、和三郎先生は、藤の子五十六人には一目置いていた。
ある日の帰り道、和三郎先生は駄菓子屋から出てきた幸造を見つけ
「幸造、何買ったんだ。」
ビクンとして、あわててポケットに入れた手を見て
「ん、幸造、その手だしてみれ、何買ったんだがなぁ」
うつむきながら出した手には、五つのかわり玉が握られていた。
「おぉ、かわり玉か。いいなぁ。君ちゃんと、千代志の分も買ったなが。えらいなぁ。」
幸造には、三年生になる妹と来年小学校に上がる弟がいることを、
担任である和三郎先生は知っていたし、家の経済状況も知っていた。
舐めているうちに色が変わってゆくかわり玉、
一個一円だったが、一日十円の小遣いの内、
その半分近くを妹弟に使う幸造を見てその優しさがいとおしかった。
「赤と桃色が君ちゃんで、黄色と緑が千代志ので、白が幸造のだな。」
「ちがうって。桃色と黄色が君子ので、赤と緑が千代志ので白が俺のなだ。」
舐めているうちに色が変わってゆくかわり玉。
幸造はいつも最初の色によって、味が違うような気がしていた。
幸造は、緑色のが一番好きだし、美味しいと思っていた。
一番美味しい緑を、千代志に食べさせたかった。
「うだども、幸造、さっき先生が「幸造」って呼んだどぎ、なしてかわり玉隠したんだ。
何もしょしがるごど、ねなだよ。妹弟思いはな、立派なことだどぉ。なぁ、幸造。」
頭をなでながら優しく言った。
右手に握られている吉備団子を見て、
「吉備団子も買ったのかぁ、いっぺ買ったな。そんたに買って いなだが。」
幸造の家庭の事情も知っている和三郎先生は幸造のそわそわしたそぶりに
「なんぼ使ったんだ」
と落ちついた声で聞いた。
「・・・・・」
「ここでちょっと待っていなさい」
和三郎先生は駄菓子屋に入ってゆき、店の人と二言三言話してポケットから小銭を払って出てきた。
吉備団子は十円だった。
「幸造・・・」
「・・・・・」
うつむく幸造の前にしゃがみ、顔を見上げて言った。
「幸造、・・・なぁ、駄目なんだや、な。」
「・・・・・」
「な、君ちゃんだって、千代志だってうれしぐねど、な。」
「・・・・・」
「きょう吉備団子みんなで分げで食って、明日かわり玉買えばいがたんでねが、な」
一日十円の小遣いを毎日もらっていることを和三郎先生は知っていた。
「千代志、緑のかわり玉食ってって言うし、君子さも、やんねば 泣ぐし・・・」
幸造の目から落ちた涙が和三郎先生のズボンに吸い込まれていった。
二人の横を、下校する子達が数人はしゃぎながら通り過ぎて行った。
「幸造、学校さ行ご、な」促す和三郎先生に
「先生っ、幸造ちゃんは、なんもだ、なんも悪ぐねなだす、わだしがまぢがたんだす、計算まぢがったんだす、
んでね、あげだなだす、んだ、あげだなだす。幸造ちゃん、君ちゃんど千代志ちゃんの面倒良ぐみるがら、
おりごうさんだがらあげだなだす、ご褒美だす、な、んだよな、幸造ちゃん」
慌てて出てきた駄菓子屋のおばさんは、和三郎と幸造の顔を交互に見ながら一気に言った。
そしてしゃがんで、エプロンの端で幸造の涙を拭いてあげながら
「幸造ちゃん、かわり玉、おばさんがらもらったんだよな、なっ。
なぁ、おばさん、幸造ちゃんえらいど、いっつも、思ってだんだよぉ。ご褒美だよなぁ、幸造ちゃん。」
幸造の頬を拭く、おばさんの声は潤み、頭をなでる手は、拭った自分の涙で濡れていた。
町内の子は自分の子の様に叱ったし、可愛がってもいた。
近くの悪ガキが、このおばさんの店から、どんせんべい二枚盗んだ時、
おばさんは阿修羅のごとく怒り、追いかけていき、
気が付いたときには隣の学区に入っていて、
それでもまだ追い続け、もう一つ向こうの学区に入るところまで来たとき、
ついにおばさん息切れし、履いていた下駄を投げつけ、
見事悪ガキの後頭部に命中させたという、近代五種の選手のような人間だった。
幸造の家の状況も知っていたし、妹弟に対する常日頃も知っていたので、
弟に緑のかわり玉を食べさせたかったという気持ちが不憫だった。
しかし、
「おばさん、私も同じ思いをしています。でもぉ、いや、だからこそ、幸造の為にならないことは・・・・。」
おばさんは、先生の言葉にはっとした。
「私と幸造と二人で話し合ってみたいと思います。
私も他に話す気はありませんので、おばさんも、そこの・・ところを・・一つ・・・。」と、
軽く会釈し、幸造の肩に優しく手をおき、
「な、幸造、学校さ行って、先生ど少し、話っこしよう、な」
こくんとうなずき、和三郎先生と学校に向かう幸造はいつもより小さく見えた。
「幸造ちゃん・・・・」
おばさんは、二人の後ろ姿を心配そうに見送った。