

(備忘録 INDEX に戻る)

【特集】
井上孝治のファインダー
孝治という父、孝治という写真家
~井上一さんが語る井上孝治の世界~
かつて福岡に井上孝治という写真家がいた。 幼少時の事故で聴覚と言葉を失いながら、かれはファインダーを通じて世界とコンタクトし続けた。
一度もプロを名乗ることなくその生涯を閉じたが、その作品は「アルル国際写真フェスティバル」をはじめ、世界的にもきわめて高い評価を得ている。
昭和30年代を中心にかれが撮り続けた福博(福岡市博多区界隈)の街並みや、そこで暮らす人々の生き生きとした表情は、今なお見る者を魅了してやまない。
「父にとっては写真がすべてだったんです。おそらく人生の何よりも」。
井上孝治さんの長男であり、福岡を代表するカメラマンでもある井上一【いのうえはじめ】さんはそう語った。
身内の一人として、同じカメラマンとして、一(はじめ)さんの目に井上孝治という人物はどのように 映っていたのだろうか。
■カメラを抱え、街へ繰り出す日々
「僕は手話ができなかったんです。もっとも親子ですから、普段の簡単な会話ならジェスチャーを交えて通じました。
子供の頃の父の記憶といっても、日曜日は遊園地に連れていってくれるとか、そういうことはなかった。
時間があればカメラを持って街へ出かけてしまう。
たまには家族と一緒の時間を過ごしてほしいと思っても、そういう意見に耳を貸す父ではなかったから、母も半ばあきらめていましたね。
春日原駅前に井上カメラ店を開業したのが昭和30年でした。この仕事は昼間に受付をして、現像は夜にまとめてやるんです。
翌朝にする引き伸ばしも当初は父がやっていましたが、母は器用だったので、引き伸ばし作業を覚えてきた。
父にとっては非常に都合がいいんですよ。夜に現像をするだけですむ。
毎日、朝からカメラを持って、嬉しそうに天神や博多駅へ出かけるようになったんです。」
当時はアマチュア写真の一大ブームの最中。全国各地でさまざまな写真コンテストが開催されていた。
賞金が1万円、賞品が3、4万円のカメラなどだったから、大卒の初任給が1万3000円の当時としてはかなり高額だったといえる。
「父はあちこちの写真コンテストで入選していました。大きいものでは世界中の写真家を集めた『国際写真サロン』で何年間も連続入賞していた。
カメラを持って毎日嬉しそうに出かけていって、気が付くと新聞に『一席井上孝治』と載ったりする。
すげえなと思うと同時に、面白そうな仕事だなと子供心にも思いました。」
一(はじめ)少年は中学生の時点で、プロのカメラマンになることを決めていたという。
写真に情熱を傾ける父を見て、同じカメラマンを志したのである。
「一度、父に相談したんです。写真が面白そうだから、カメラマンになりたい、と。
父は写真の専門学校が東京にあることを教えてくれて、
自分はろうあ者で行けなかったけれども、おまえはやってみろと言ってくれた。
専門学校を卒業して、丁稚奉公でプロのスタジオに入りました。
広告写真の世界です。しかしこの世界は、父のように好き勝手に写真を撮れるわけではない。
いろいろな制約があって、その中で写真を撮らなければならないんです。
仕事だから当たり前なんだけど、そんなに面白いものじゃない。
そのとき、父を思い出して、分かったんです。父は道楽で写真を撮っていたんだな、と。
僕は今では広告写真のプロであって、そのことには誇りを持っています。
ただ、父があんなに毎日嬉しそうに撮影に出かけていたのは、
自分の写真を自分が好きなように撮っていたからなんだ、という気がします。
写真集『想い出の街』を編集してくれた人は、
いちばん最初に載せるのは氷柱をなめる少年の写真、最後は犬の後ろ姿の写真、とまず決めていたそうです。
■百貨店のキャンペーンと『想い出の街』
孝治さんが毎日福博の街へ出て、
撮りためていた写真──後に写真集『想い出の街』を飾ることになった作品群──は、
長い間、井上家の押し入れに眠ったままだった。
それが日の目を見たのは1989年。老舗の百貨店、岩田屋がキャンペーンに使うため、
福岡の古い写真を探しており、一(はじめ)さんが相談を受けたのがきっかけだった。
「大量のネガが押し入れの段ボールに入っていました。
プリントもされていない状態でしたが、ネガを光に透かすと、
それだけですごいと分かる写真がたくさんあるんです。
構図が独特で、しかも視線が限りなく温かくて……。
ショックでした。コンテストで入選しまくっていた頃の写真というのは、いま思うとコンテスト用に撮影した写真なんですね。
コンテスト用の写真というのは、あるテーマが決まっていて、それに沿った何百点の写真から選ばれるわけですから、
アングルが新鮮とか、目立つためのテクニックがある。
でも、『想い出の街』の写真は、まったく違うタイプの写真だった。
そこには、あざとさといったものが一切排除されていて、ごくごく自然で、しかも撮影した人間の温かみがじわっと伝わってくるようでした。
写真を見る者に感動を与えるためには、実にいろいろな要素が必要だと思います。構図、光の具合、被写体の表情、アングル。
父の写真はそれらをすべて兼ね備えていた。
父の作品を見て僕が受けたショックというのは、そういうことでした。
■井上孝治が遺した福岡の街
昭和30年代、孝治さんが毎日のように撮り続けた福博の街。
今、私たちはかれの写真によって当時の街の様子や、
生活する人々の表情を目の当たりにすることができる。
そこに写し出されたものの多くは、私たちがどこかで失ってしまった風景である。
「当時は日本が経済成長に差し掛かった頃で、まだみんなが貧しかった時代です。
ほとんどの道路はまだ舗装されていなくて、雨が降ればぬかるむし、乾けば砂ぼこりが立つ。
折々の表情があったんです。車も少なかったから、子供は道路で遊んで、
おばちゃんは家の外へ出て夕飯の煮炊きをしていた。
生活の匂いが道路にまで充満していたんです。ところが道路が舗装されて
、
車の通行量も増え、遊びや生活は家の中で完結するようになる。
道路の変化とともに、生活感のある風景は失われて、道路は人が行き来するだけの場所になった。
そうすると父にとっての被写体が、街にはなくなってくるんです。
父の写真展を開くと、見に来てくれた人、特に僕と同じ年代かそれ以上の人は、
自分もそうだったと共感を覚えるようです。
その時代の記憶がよみがえってくるんでしょう。
一枚の写真の前にずっと立ちつくしたり、涙を流したりする人がいっぱいいる。
まったく知らない人同士が当時の思い出話に花を咲かせることも。
人を感動させたり、昔を思い起こさせたり──
そういう、写真が本来持っているはずの力が、父の写真にはあるのでしょうね。」
井上 一 氏 談

井上孝治氏のご長男、一氏から当方の掲示板に書き込みが有った。
当日を楽しみにしていたが、2011年3月11日のあの大震災があり、知人の消息を求めている間に放送時間は過ぎ去った。
なので、あの状況下、放送されたかも知らない。ご紹介下さった一氏には申し訳ないと思っております。
放送日の2011年3月13日、消息を捜し求めた陸前高田市の知人の遺体が発見された事を知った。
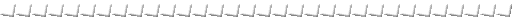
[特集]井上孝治のファインダー
~井上孝治の生涯をたどったフランスの映像作家
ブリジッド・ルメーヌさんに聞く~
井上孝治さんに対する海外での評価の高さは、彼の作品の普遍性を物語る。
フランスの映像作家ブリジット・ルメーヌさんも彼の作品に感銘を受け、1996年に19分のモノクロ映画『私を見てください。私もあなたを見ます。
聾者の写真家井上孝治』、98年にドキュメンタリービデオ『井上孝治──表象を超えた写真家』を発表している。
彼女が井上さんの作品に初めて触れたのは93年のアルル国際写真フェスティバル。
彼の写真のどこに魅力を感じたのか、来日したルメーヌさんに話をうかがった。
■音楽にも似たイントネーションで語りかけてきた写真
──井上孝治さんの写真を見て何を感じましたか。
「私に語りかけてくれるような気がしました。日本の写真ですから、私の知らない世界なのに、かつて自分で観たような世界を感じました。
彼がろうあ者であることは知っていたのですが、実際に写真を見ると普通の写真とはまったく違うという印象が強かった。
ひと言で言うと、顔の表現が違います。ろうあ者とのコミュニケーションでは表現にイントネーションを付けなければなりません。
表情や表現の、いうなれば音楽にも似た強弱をコウジ・イノウエの写真のなかに見ることができたのです」
──1作目の映画『私を見てください……』は全編井上孝治さんの写真と、手話で構成されています。
あのような表現は以前から採られていたのですか。
「ろうあ者の俳優に出演してもらい、手話を美しく見せる必要があると考えていました。
それに、イノウエの写真から私自身が受けた感銘を強く表現したかった。
手話についてはフランスやドイツ、それから日本でもあまり詳しく知られていませんが、
非常に創造性の高いコミュニケーションであることを知ってもらいたかったのです」
──2作目の『井上孝治──表象を超えた写真家』はドキュメンタリー形式を採られましたが。
「イノウエの家族に会いたかったし、彼が実際に写真を撮った場所も見てみたかった。
ドキュメンタリーという形になった理由はそれに尽きます。それに他の写真のネガも見たかったものですから」
──福岡という土地も彼の代表作『想い出の街』の頃とはだいぶ違っていたのでは?
「最初の印象ではまったく違うと思いました。
ただ、何回か行くうちに、確かに街は変わったのだろうが、そこに住む人間はおそらく変わっていないと思うようになりました。
考え方そのものは、イノウエが撮った写真のなかの人々と変わっていない。そう考えるようになったのです。」
■<視覚の知性>をテーマに3作目の撮影も進行中
──
──井上さん本人と直接面識はないわけですが、ルメーヌさんは彼がどのような人だったと考えているのですか。
「もちろん彼自身の立場になることはできませんので、私のなかではということになりますが……。
彼は知性が高く、いろいろなことに興味を持っていたと思いますし、常に人とのコミュニケーションを持ちたいと考えていた人だったと思います。
とくに<視覚の知性>が非常に高かったと考えていますので、それをテーマに今、沖縄で撮影しているところです。
彼は芸術家である以上に、ろうあ者のことを考えていた人だとも思います。
おそらく日本だけではなく、世界中のろうあ者のことを考えていたのではないでしょうか」
──<視覚の知性>というのは、ルメーヌさんが追求するテーマと共通しているのですか。
「追求していきたいテーマです。なぜなら、私自身、ろうあ者である祖父母に育てられましたから。
今、香港をはじめとして世界中でろうあ者の視覚の知性というものが注目を集めています。
彼らの知性は、建築家やチェス競技者、あるいは数学者など、
最初にイメージを持ってから仕事を進めていく人々のそれと共通していると私は考えています。
手話も究極的には感性を表現できる手段だと思いますから、私自身こうした方面での作品を作っていきたいと思います」
ブリジット・ルメーヌ
フランス生まれ。社会学者。美学博士号を取得。
報道雑誌「レクスプレス」誌で編集などの仕事を経た後、88年からドキュメンタリーの映像作家として活躍している。
障害者や児童虐待などを扱うドキュメンタリー映画を数多く制作。
特に「耳の聞こえない人の文化」「視覚的知性」を伝えることをテーマとしている。ろう者の祖父母に育てられたことから、自らの母語は「手話」だという。
■発見された三十年前のフィルム>
平成元年、福岡の一人のアマチュア写真家が、にわかに注目を浴びた。
地元の百貨店「岩田屋」が、昭和三十年前後の福岡の街や人々を撮ったモノクロ写真を使って
「想い出の街」というシリーズ広告を展開したのである。
そこには、日本人が記憶の奥底にしまいこんでいた昭和の原風景が、鮮やかに写し取られていた。
敗戦のショックからようやく立ち直ったころの、まだ道も舗装されていない地方都市のさりげない日常風景。
物は乏しく、生活は苦しかった。しかし、写真の中の人々の表情は生き生きと輝き、
温かい人情があふれ、家族や兄弟や人間同士の絆が自然に表れている……。
その広告の写真には、人々の目を引きつけ、思わず立ち止まらせてしまう「何か」があった。
実は、それを撮ったのが、井上孝治という・ろうあ・の写真家だった。
音のない世界で生きる彼が出逢った「写真」。それは、声で話す代わりに自分を表現する言葉そのものだった。
カメラのファインダーを通して、彼は世界とコミュニケーションをしていたのである。
ただし、その写真の大半は発表されることもなく、押し入れの中で三十年以上眠っていた。
福岡の古い写真を探していた岩田屋の販促課長が、孝治の長男で商業写真家の一に声を掛けなければ、
その大量のフィルムが日の目を見ることはなかったに違いない。
同年、孝治は初めての写真展を開催することになり、同時に写真集『想い出の街』も刊行する。
その時すでに七十歳。以後、平成五年に亡くなるまでの人生最後の五年間は、彼自身も家族も想像さえしなかった、ドラマに次ぐドラマの連続だった。
■聾学校時代に写真と出逢う
井上孝治は大正八年(一九一九年)、福岡市箔屋町(現・博多区店屋町)で樽桶製造業を営む家の長男として生まれた。
しかし、三歳の時に、自宅の二階からの転落事故が原因で、聴力を失い、話せなくなった。
当時、現在以上に障害者は様々な差別にさらされていた。
例えば、聾学校も義務教育ではなく、家庭の経済事情で、学校に行きたくても行けない子どもも少なくなかった。
その点、孝治は幸運だった。彼が七歳の時、一家は福岡県粕屋郡宇美町に移転し、
酒樽製造で成功して町内でも指折りの資産家となったのである。
恵まれた環境で育った孝治は、昭和二年に福岡県立福岡聾学校に入学し、そこで青春時代を謳歌する。
学校では職業教育として木工科で学び、家具製造の技術を身につけたが、
在学中にすでに玩具のようなカメラを手に入れ、自分で撮影から現像、プリントまでこなすようになっていた。
孝治が写真に興味を持つようになったのは、父清一の影響が大きい。
清一は当時、大変高価なドイツ製のカメラを数台購入して、趣味で写真に熱中していた。
孝治が写真をやろうと決心したのは、
その清一から聾学校中等部の卒業祝いにもらった「ミノルタフレックス」という本格的な二眼レフカメラを手にした時だった。
しかし、そのころ、日本は中国との戦争が泥沼化しつつあり、間もなく太平洋戦争に突入する。
フィルムや材料も配給制になり、撮影自体が困難な時代になっていく。
孝治は地元の写真クラブに入会して「興亜写真報国会」の活動に従事した。
これは、出征軍人の家族の写真を撮影して戦地に送るもので、そのためにフィルムの配給を受けることができたのである。
戦時中、一家は博多に戻って旅館と待合を営業していたが、昭和二十年六月十九日の福岡大空襲で全焼。
仕方なく、再び宇美町へ疎開してそこで終戦を迎える。その時、孝治には妻子がいた。三年前に結婚した妻のミツエと長男の一である。
■米軍占領下の沖縄を撮る
戦後、文字通り・写真三昧・の生活を送った夫の陰で、ミツエが家族の生活を支えた事実は忘れてはならないだろう。
昭和三十年、二人は春日市で「井上カメラ店」という写真の現像・プリントと機材販売を行う店を始めたが、
当時、数々のコンテストで上位に入賞していた孝治は自分の撮影のために毎日外出してしまうので、
ミツエは客の応対をし、じきに見よう見まねで現像までやり始めた。
子どもも三人に増えていたが、孝治は家庭のことはすべてミツエに任せきりだった。
しかし、その一方で彼には、家族でさえよく知らないろうあ者のリーダーとしての・顔・があった。
福岡県のろうあ団体の会長・相談役として活躍し、ろうあ会館を建設、全国に先駆けてろうあ者の運転免許取得を実現させている。
また、福岡だけでなく、全国のろうあ写真家を組織して日本初の「全日本ろうあ写真連盟」を設立、初代会長も務めた。
これらは、孝治の存在を抜きにしては恐らく実現しなかっただろうといわれている。
また、特筆すべきは、昭和三十四年に米軍占領下の沖縄に約四週間滞在して、当時の庶民の姿を数多くの写真に残したことである。
この時期の沖縄のこうした写真はほかにはあまり存在せず、非常に貴重なドキュメントになっている。
平成元年、「想い出の街」のフィルムと同じ箱から発見されたこのフィルムは、沖縄の写真界の人々を驚かせた。
そして、平成二年、ボランティアの有志の熱意で、孝治の沖縄の写真展が那覇市で開催され、翌年には写真集も制作されたのである。
会場に詰めかけた沖縄の人々は、自分たちが過ごしてきた長い苦難の歳月を振り返り、写真の前に立ち尽くした。
だれもが流れる涙を抑えることができなかった。それはまさに写真の偉大な力だった。
お金のためでも、名誉のためでもなく、ただ自分の心の赴くままに、撮りたいものをひたすら撮り続けてきた孝治にとって、
晩年になって得た、人々のこうした反応に優る喜びはなかったに違いない。
■世界共通の言葉としての写真
そんな孝治の作品に魅せられたのは、日本人だけではない。
平成二年冬、まずフランスの「パリ写真月間」で、「想い出の街」シリーズが現代日本を代表する広告写真の一つとして展示され、
平成五年には南フランスの「アルル国際写真フェスティバル」の招待作家に選ばれた。
世界の写真祭の草分けであるこのフェスティバルに、アマチュアの彼が、
リチャード・アヴェドンなど世界一流の写真家と同等の扱いで招聘されたのである。
だが、その招待状が届いた時、孝治は入院中だった。
そして、フェスティバルのわずか二カ月前に肺ガンのため永眠する。
ついに孝治本人はアルル訪問を果たせなかったが、現地では遺作展が開かれ、
彼の作品と人生は地元の新聞等でも取り上げられ、観客を感動させた。
彼が撮った写真は世界共通の言葉として、海外でも人々の心を動かしたのだった。
この時、孝治の作品は、「写真の神様」として日本でも名高いアンリ・カルティエ=ブレッソンの作風に通じるものがあると絶賛され、
また、「アルル名誉市民」に認定される栄誉にも浴している。
生涯アマチュアで通した写真家の個展が、死後も繰り返し開催され、幅広い世代のファンを獲得し、
新規に写真集が刊行される(平成十二年秋予定)というのは稀有なことだろう。
彼は障害者ではあったが、写真という映像表現の分野ではそれがマイナスではなくプラスになった。
失った聴覚の代わりに得た卓越した視覚によって、彼は被写体の微妙な動きも見逃さず、
映画の一場面を思わせる・決定的瞬間・をとらえることに成功している。
だからこそ、ただ単に古い懐かしい写真ではなく、時代を超えて普遍的に人々の心を打つ作品となっているのである。
平成十二年春、東京都庁内のギャラリーで井上孝治写真展「音のない記憶」が開催された。
会場のノートには様々な世代から様々なメッセージが残された。
「ノスタルジーだけではないリアルな写真。このような人やものが文化なんですね。
私の知らない日本の風景が、知らないはずなのに何か暖かいものを思い出させるような気がしました」(十代・女)
「懐かしさと同時に、苦しかった時代を共感できます。
昭和二十年に焼野原に立っていた者として特に写真を通して感じるのは、
家族愛と兄弟愛が無ければ生きられなかったということ」(六十代・男)
写真家・井上孝治が遺した時代の「記憶」は、人々が心に抱く原風景とも交感しつつ、永遠に生き続けることだろう。
井上孝治氏について・・・追記に進む
このページのTOPへ戻る

![]()

![]()